COLUMN
コラム
療法食って?病気を普段の食事でサポートする頼もしい味方です!
こんにちは、港北にっぱ動物病院です!
「療法食を進められたことがあるけれど、普段の食事と何が違うの?」
一度は疑問に思ったことはないでしょうか?
ここで今回は療法食についてお話ししたいと思います。
療法食ってなに?
療法食は特定の疾患等に対処するため治療の一環として与える食事となります。
そのためそれぞれの病状に合わせた成分や割合で作られています。自己判断で誤った与え方をすると、かえって健康を害する可能性もあるため、獣医師の診断と指導に沿って与えることが重要になります。
ペットフードを分類すると総合栄養食・療法食・その他目的食・間食に分けられます。
【総合栄養食】
総合栄養食と水だけで健康が維持できるバランスの取れた食事。年齢に合わせて必要な栄養基準を設けている
【療法食】
特定の病気や健康状態に対応できるよう、栄養バランスが調整されており獣医師の診断と指導の下で与える食事
【間食】
おやつ類(ジャーキー・ビスケット・ガム・液状おやつなど)給与限度量は、原則として1日当たりのエネルギー所要量の10-20%以内に抑える
【その他の目的食】
要は“おかず”のことを指し嗜好性も高く、エネルギーや栄養補給を重視したごはんのため主食には適していません。
動物病院で取り扱っている療法食にはこのマークがパッケージに表示されています。
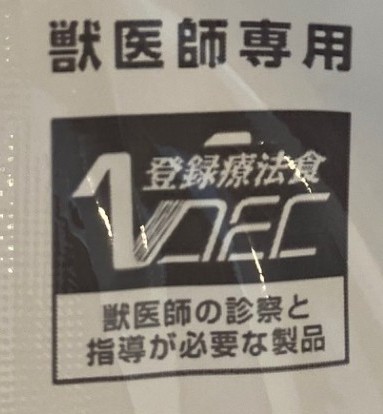
このマークは療法食基準に適合することが確認され、一般社団法人獣医療法食評価センターに登録された療法食に表示されます。市販での取り扱いが難しく獣医師の診断と指導が必要となります。
療法食の種類
療法食も様々な種類が出ており、主な療法食をいくつかご紹介したいと思います。
【消化器疾患用】
下痢や便秘、嘔吐などの消化器疾患を繰り返しやすい子に食物繊維を増やし、腸内バランスを整える作用が含まれる消化に配慮した食事で、便秘の子には薬に頼らず便を出しやすくできたり、下痢をしやすい子の頻度が劇的に改善するケースもみられます。
【尿路疾患用】
頻尿・排尿痛・血尿などの症状を引き起こす膀胱炎や尿石症に対して再発防止・予防に特化した食事で、ストルバイトのような食事を変更することで溶かすことができる膀胱結石、尿結石の場合にとても有効です。シュウ酸カルシウムのような溶けない石に対しても、シュウ酸カルシウムができにくくなるようにするフードも現在では販売されていますので獣医師に相談してみてくださいね。
【腎臓疾患用】
腎機能が低下することで血液中に老廃物や毒素が増えやすくなり効率的に排出できなくなります。原因となるタンパク質やリンの含有量を制限し腎臓への負担を抑えた食事で、血液中のBUNやIPの上昇を抑えるためには食事療法はとても強い味方になってくれます。腎機能を長持ちさせるためにもぜひ食べてもらいたいお食事です。
【心臓疾患】
心臓疾患により心臓の働きが低下すると、塩分を効率的に排出できなくなり体内の水分が溜まりやすくなります。ナトリウム(塩分)の含有量を制限し心臓への負担を抑えた食事です。心臓病に影響すると言われているタウリンなどの栄養素もしっかりコントロールされています。現在では猫の肥大型心筋症に対する療法食もでてきました。心臓病も長期持続的に付き合っていけなければいけない疾患で、治るわけではないので少しでも病気の進行を抑えるために、療法力はとても良い選択肢だと思っています。
【皮膚疾患】
皮膚トラブルの原因になるアレルゲンを細かく加水分解してアレルギー反応を起こしにくくするような低アレルゲン食や、皮膚に必要な栄養素をバランスよく摂取し、かつ皮膚のバリア機能を高めるためのオメガ3などを配合した皮膚を強くする療法食などがあります。その子にあった食事を診察室で先生がお話しながら好みとご相談しながら決めていきます。
【体重管理用】
肥満は糖尿病のリスクを4倍にしますし、その他心臓疾患、呼吸器疾患、高脂血症、肝障害などさまざまなリスクを増大させます。体重を減らすだけでも健康寿命はのびると考えて、体型をしっかりみていきましょう。体重管理用の療法食は摂取カロリーを抑えつつ必要な栄養素や食物繊維を多く含み満腹感を得られやすい食事になっています。ある程度量を食べてもカロリーが低いので少しずつやせることができます。
このようにそれぞれ病状に特化した食事が療法食となっています。




当院ではこのように食事を待合にて紹介しており、先生が状態に応じて選択したりご相談をうけてお勧めしたりしています。
療法食をなかなか食べてくれない・・・
食べが悪い時などにできる工夫・対処をいくつかご紹介したいと思います。
①温める
ドライフード、ウェットフードも温めることで香りや風味が増し嗜好性が良くなります。電子レンジで人肌程度に温め、与える前には熱すぎないか確認をしてあげましょう。ドライフードの場合はフライパンで乾煎りするのもおすすめです。香ばしくなります。
②ふやかす
ぬるま湯でふやかす事で香りや風味が増すとともに、柔らかくなるため食べやすくなります。
③少しずつ与える
一度に沢山与えるのではなく、その時の体調に合わせ少量を回数分けてあげてみましょう。
療法食への切り替え方
基本的には7日間を目安に徐々に療法食に切り替えていきます。もちろん7日以上切り替えにかかる場合もありますが、その子に合ったペースで焦らず切り替えていきましょう。切り替えもいきなり変えてしまうと食べてくれない場合があるため、食べ慣れていた食事と療法食を少しずつ混ぜながら最終的には療法食に切り替えていきます。
病状によっては切り替え方が変わることもあるので必ず獣医さんに確認をしましょう。
最後に・・・
療法食も一つの治療の一環として気軽に取り入れられる治療法のひとつです。気になる食事などありましたら気軽にご相談ください!

